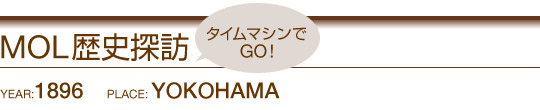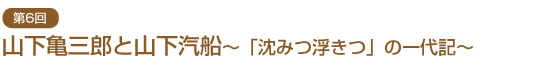家出少年から放蕩息子に
| 大当たりをする前は、愛媛県宇和島の中学校を落第し、15歳のとき、「太政大臣三条実美のようになる」と言って家出したものの、東京に出てきては明治法律学校を中途落第退学したという。3、4年の商店奉公も一向に浮かばず、1894(明治27)年、資本皆無で石炭商売に手を染めた経歴。その間、親のすねをかじり、郷里で母親が氏神に日参し「コレラにかかって死んでくれ」と祈念したほど、相当の親不孝者である。 |
石炭商から船持ちへ
| 石炭商として独立後3年、ようやく商売が回り始めた1899( 明治32)年33歳のとき、初めての直積み石炭600トンの引き取りで、回漕店からの運賃(720円)支払い請求に困惑する亀三郎。「運賃などというものは石炭を売込みその代金を得てから払うもので、先に払う理屈がない」。あまりの無知を聞き及んだ知己の立て替えでその場をしのいだが、「運賃を先取りできるなんて、こんな小気味いい商売はない、石炭商より船持ちだ」という想いが再燃する。 石炭商売に精を出して蓄えた資金も1万円になった1903(明治36)年。どうも日露の関係が面白くないと、12万円で売りに出ていた英国船「ベンベニュー号」(2,372トン)の頭金に1万円をはたき、石炭商の弟分である松永安左衛門、そのパートナー福沢桃介らの協力もあり、苦労の末にサミュエル商会から購入成功、念願の船主となる。「土佐丸」の向こうを張って「喜佐方丸」と命名した。 持たねばならぬ、持ちたい信念だけで船主となったものの、経験も知識もなく、燃料代さえ稼げず赤字を垂れ流し、2 ? 3航海もすればパンク寸前という眠れない日々が続く。そんな中でも、御用船に聞き及ぶや、徳富蘇峰のチャンネルで海軍省へ抜け目なく直談判。半年過ぎても音沙汰なく暮れも押し詰まった12月26日、資金工面に門司まで出かけていた亀三郎に届いた至急電報「ゴヨウセンノ メイ クダル」。 名前に似合わず素早い亀三郎。三井の上海行き石炭満載で佐々港出帆目前の本船に(ここは英断一番、国家の御用に対しては三井などにグズグズ言わさぬ)即時、横浜廻航を指示(世の中は、山下が石炭を積んだまま逃げた、と騒然)。夜行で門司を発ち、大阪で三井の支店長に事後了解を求めた後、横浜へ戻って陸揚げの手配、海軍に引き渡すという早わざ。この間3 ? 4昼夜、無我夢中でどこをどう歩いたか記憶にないという。 |
船を持った動機
| さかのぼること7年前の1896(明治29)年3月15日、横浜。駆け出しの石炭商亀三郎は朝、伊勢山の家で、日本郵船の欧州航路第一船「土佐丸」の汽笛を聞き、横浜の海がロンドンに通じた気がしてじっとしておれず、ビールの小瓶1本もって近くの伊勢山皇大神宮境内に駆け登り、茶碗で乾杯しながら、他日自分も船を持ち英米とつないでみたいと夢想し、これが海運業を志す原点となった、と回想している。 世間のにおいに敏感な亀三郎、翌年1904(明治37)年2月宣戦布告さるや、「喜佐方丸」姉妹船「サンダー号」も購入、石炭も買い集め、一旗揚げることに成功する。 |
「喜佐方丸」と「吉田丸」 明治36年(1903)外国人商社Samuelから売りに出ていた中古船を買い取り郷里喜佐方村の名前を冠して「喜佐方丸」と命名した。 2隻目を「第二喜佐方丸」、3隻目を「第三喜佐方丸」と命名している。 |
 |
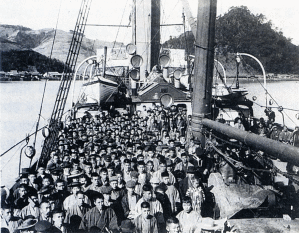 |
大正6年に建造した船にはやはり故郷吉田町の名前を冠し「吉田丸」と名付けその後も「第一吉田丸」、「第二吉田丸」、「第三吉田丸」と名づけた。 「喜佐方丸」は明治39年(1906)には初めて故郷に回航され、吉田町の人々に大歓迎された。 |
反動不況の沈没期
| 短期間でもうけた亀三郎、渋沢栄一の依頼で引き受けた小樽木材株式600万円が戦後反動不況で紙くずになるなど、沈むのも早かった。途方に暮れてレールの上に身を横たえたこともあったというが何とか踏みとどまり、資金を頼みに伺った大倉喜八郎の「山下君、僕の境遇を直ちにあげるよ。代わりに君の歳と替えてくれたまえ」という言葉に奮い立った。 |
小田原
対潮閣
| 囲碁も将棋も知らねば、ゴルフにもトランプにも興味なし。気分転換に居場所を変える必要もあり、また読書ができない亀三郎、耳学問の情報収集に客を呼ぶ必要性から、高輪の本邸以外に各地に別荘を所有。政財界人・文人墨客たちが好んで住まった小田原の対潮閣もその一つ。 豪傑松下軍治が手掛けた木曾御料林の檜を使い豪壮な邸宅であったが、病没後の大正5年売物に出されるも買い手がつかず、頼まれて亀三郎が15万円で購入。その水道設備を利用していた閑院宮家、山縣有朋、益田孝たちにいたく喜ばれた。以来、懇意となった古稀庵主山縣元帥に造園を依頼、「口出し無し・期限無し・予算無制限」の乱暴な3条件を、「この大戦中は稼ぐので、元帥はその半月のもうけも使えまい」と即座に了承。その完成をもって元帥により「対潮閣」と命名さる。その掛け物 「うち渡す相模の海を池にして仰ぐ箱根は庭の築山」 が豪壮さを物語るが、残念なことに関東大震災で崩壊した(本人は、「綺麗さっぱり解消された」という)。 『坂の上の雲』の主人公「天気晴朗なれども波高し」で有名な秋山真之提督は、療養中の1918(大正7)年2月4日逗留先の友人宅にて再発した盲腸炎が原因で没したが、その友人こそNHKドラマよろしく「淳さん」と呼び合う仲の亀三郎であり、対潮閣の二階が提督最期の地である。現在は観光スポットとして碑が立つ。日露開戦前の風向きについて真之情報もあったのかもしれない。 |
社会還元
| 自分が今日あるは厳格に育ててくれた母親のおかげであるとして、郷里に女学校を2校建設するなど子女教育に関心の高かった亀三郎は、1940(昭和15)年、軍人・軍属の子弟教育のため陸海軍に何と1,000万円を寄付し、これを基金に?山水育英会が設立された。戦後は小澤征爾も輩出した桐朋学園に引き継がれている。 前年の1939(昭和14)年に竣工した大阪商船の南米航路代表的客船「あるぜんちな丸」の船価が約1,000万円。また1940(昭和15)年度の絶頂にあった山下汽船の営業利益が1,344万円。その心意気が想像できようというもの。 |
故郷への社会貢献
|
(1)喜佐方小学校への寄付 明治38年と明治39年、亀三郎の故郷にある喜佐方小学校の基本財産壱阡円、敷地買収費壱阡円寄付これらの援助により明治41年喜佐方尋常小学校の新校舎が落成した。 又、大正11年同校の増築工事費の一部として七阡円を寄付、昭和12年には校庭拡張費の一部として壱万円の寄付をした。 さらに昭和17年に山下講堂を工事費の一切を山下亀三郎が寄付し建築された。 (2)喜佐方村図書館への寄付 大正8年(1919)、建築費4,600円で喜佐方村久保に木造2階建て35坪の図書館を設立。 (3)筋への道路と防波堤 明治41年(1908)喜佐方から堀切を経て筋に通じる筋道路が起工され壱阡円寄付。 大正6年(1917)筋に1500坪の別荘が造られこの別荘があった吉田町白浦外に現在も穏やかな内港をつくりだしている防波堤を寄付。 |
| ◎奥南運河の建設 昭和2年(1927)亀三郎の援助で吉田町奥浦に奥南運河を建設、西宇和郡の小村から南予のハブである宇和島に向かう人々は漁船に身を託し奥南運河を通過して宇和島に向かったのである、大崎鼻や法花津湾口は難所も多く、天候を気にしながら大崎鼻から一気に奥南運河をめざして航行したことであろう。 |
 |
| (4)二つの女学校 大正6年(1917)吉田町に山下実科女学校を開校し大正13年(1924)には4年制の高等女学校に組織替えし、私立山下女学校と改称した。 大正9年(1920)母の郷里三瓶町に第二山下実科学校を開校。こちらも大正13年に4年制の高等女学校に組織替えし私立山下高等女学校と改称した。 (5)吉田病院 大正10年(1921)診療を開始した吉田町外五ケ村衛生組合立吉田病院の創設について建設費用の一部として弐萬五阡円を寄付、亀三郎は医師の人選についても、かねてかこころ易かった東京帝国大学の真鍋喜一郎を紹介、その結果開院すると帝大出身の名医がいる総合病院として吉田、宇和、野村方面ばかりか、海を越えて大分方面からも患者が訪れた。 (6)吉田中学校 大正12年(1923)第1回入学式を挙行した吉田中学校づくりについても、亀三郎は、清家吉次郎町長をバックアップした。 やがてこの学校は、昭和13年に県立吉田工業高校となり更に昭和25年には私立山下高等学校を併合した。 (7)喜佐方トンネル 昭和15年(1940)喜佐方隧道の工事が開始〜昭和17年完成、これにより喜佐方から隧道を通って立間まで吉田を迂回せずに直通で行けるようになった。 この隧道づくりでも、大実業家・山下亀三郎の富が幾多の困難を吹き飛ばした。 |
【山下亀三郎】1867(慶応3)年〜 1944(昭和19)年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||