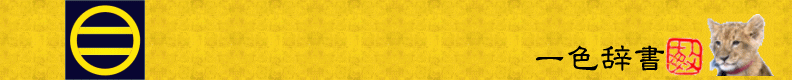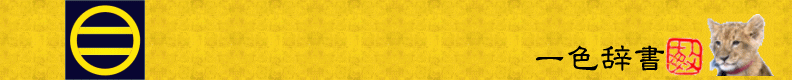| ◆青木一重という人とは・・・ |
 |
| 青木一重公 |
◎青木氏は美濃の豪族の出で、父重直が土岐氏・斉藤氏その後、織田信長や豊臣秀吉に仕え秀吉から豊島郡(現在の箕面市の平尾・西小路・桜・牧落地域その他)で二千石を与えられ麻田藩の基礎を築いた。
◎その長男一重は天文20年美濃国に生まれ、徳川家康の家臣となり姉川の戦いで越前随一の猛将と知られた真柄十郎左衛門を討ち取って織田・徳川連合軍の逆転勝利の突破口を作り、その勇名を天下に馳せた。
※真柄十郎左衛門は朝倉義景の家臣で身長196㎝、体重252㎏をこえたとされる歴史上最も大きい太刀の使い手としられた勇猛果敢な武将
○その後、豊臣秀吉の旗本の黄母衣衆で使番を勤め七手組と呼ばれていた豊臣親衛隊の大将の一人となり秀吉亡き後秀頼に仕えたが七手組親衛隊は秀頼の身辺を護ることが任務である為関ヶ原の戦には彼らは出陣することは無かった。
※七手組は秀吉が存命中に約1万の精鋭を7つの部隊にわけ、豊臣家の身辺警護から朝廷への儀礼などに用いた部隊。
組頭は概ね1万石程度の所領を持っている。秀吉死後は豊臣秀頼に仕え、関ヶ原の戦いでは主に大坂城の警護任務に終始した。
○天正十三年摂津豊島郡で領地を与えられた他、その後伊予の周敷、備中にも領地加給された。
○天正十六年四月十四日、正親町天皇が聚楽第へ行幸された時、秀吉の家来衆にも叙位があり青木一重は従五位下民部少輔に叙せられ以後、青木民部と呼ばれた。
○慶長十九年の大阪冬の陣には七手組組頭として参戦したが冬の陣の講和がなった後、彼は和議の謝礼の使者とし家康の元へ、すると家康は、これから上洛するのでそこで使いの趣を聞こうと云う、そこで京に行くと家康は板倉勝重に、一重に京に留めるよう命じもし逃げ帰るならば、私に仕えている弟の可直を殺すと云えと命じ彼がやむを得ず京に留まっているうちに夏の陣になり、大阪城は落城した。
※大阪夏の陣には一重の養子、青木駿河守正重が一党を引き連れ参戦・・・
彼は仕方なく剃髪して出家しましたが、家康は彼を二条城に召し出して、再びその配下に加え所領を安堵しました以前からの所領の一万石はそのままで、更に父重直の死後は、父の所領も加えて一万二千石を領し家督を退く時に父の所領であった二千石は弟可直に譲ったので一万石の大名となり豊島郡麻田村、現在の豊中市蛍池に陣屋を構え麻田藩として幕末まで続いた。
|
|
| ◎青木一重(摂津麻田藩初代)の周敷村支配 |
○天正の陣(秀吉の四国征伐)以後の周敷村の領主について調べてみると、天正十三年八月、伊予国は小早川隆景の支配となりましたが約2年で終わり隆景の後、東予地方へは秀吉子飼いの福島正則が来て東予五郡十一万千二百石を領しましたが、この時、当地周敷村は福島正則の領地にならず、天正十五年九月周布郡三津屋村、北条村、周敷村、石田村など四千三百国は摂津国に領地を持つ青木民部の飛領地となり、民部の養子、青木駿河守正重(小寺宮内右衛門)が代官として来て当地を支配した。
|
|
|